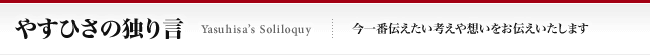2021/02/07(日) NO.854号
「有事」モードへ完全転換する覚悟
わが国での新型コロナウィルス感染者第一号から一年余り経った。わが国で変わらないことがひとつある。それは、厚労省をはじめ、政府は一貫して「平時」モードから抜け切れず、一向に、覚悟を決めた「有事」モードに完全転換し切れていないことだ。先日成立した特措法、感染症法改正法もその典型だと私は思う。
最大の焦点は、「有事には国が司令塔となり、責任を一手に負う」、すなわち「平時」通り、都道府県任せにはしない、ということを明確にし、全てを「有事」モードに切り替え、地方の声はよく聞きながら、最後は国が決めることだ。そうした大事なモードの大転換なしによって、本来助かる命が失われて来たのではないか、と与党議員の一人として責任を重く感じる。
昨年12月以降、全国で自宅療養中に亡くなった方々は少なくとも27人に上るという。そして、昨日の一部報道によると、その原因は第3波による感染者急増により宿泊施設確保が追いつかず、自宅療養者が急増、保健所の対応が追い付かず、死亡者が続出した、となっている。
この中には、いくつかの重要な認識違いがあり、その論理の裏にも、実は「平時」の発想のままで「有事」モードの体制構築ができていない結果、深刻な事態を招いているのでは、とみられる点が多々ある。
一番大きな認識違いからくる自宅待機中の死亡事例の根源的原因の一つは、新型コロナ感染症という、今だ未知な部分が多い、手強い感染症でありながら、相変わらず、陽性患者となった途端に保健所を中心とした「公衆衛生」の世界に患者を留め置き、それまで慣れ親しんできたかかりつけ医等の「地域医療」から隔絶させることだ。
保健所の職員の皆さんは、健康観察のため、電話で献身的に患者を気遣いながら、容体などを聞いてくれるものの、業務はパンク状態。病状が悪化しながら入院先を確保できず、患者は医師と話ができないうちに自宅で亡くなっていくケースが多いという。地域で自宅療養者の治療に当たっている数少ない医師の一人が昨日のテレビ画面を通じ「家族だけが保健所に入院先を探してもらえるよう折衝できるのであり、われわれ医師はそれができない」と、「有事」でありながら、「平時」通り「公衆衛生」優位が貫かれてしまう、もどかしい思いを吐露される姿が印象的だった。
昨年6月に私が自民党行革推進本部長として取りまとめた提言(注1)では、感染症危機対応体制に関し、「『公衆衛生」と『地域・臨床医療』の有機的一体化」を感染症有事における国家のガバナンス確立に向けての抜本改革の3本柱の重要なひとつとして提言した。コロナ危機を有効に乗り切ったと世界からみられている台湾、ベトナム、中国、韓国、などは、SARS、新型インフルエンザ、MARSなど感染症危機の教訓から、実際に「公衆衛生」と「地域臨床医療」との有機的一体化を既に実現し、今回もそれが機能しているという。陽性者の健康観察や入院先の調整を保健所、公衆衛生が独占する必然性はない。
二番目の問題は、宿泊療養について、「平時」の発想のままで「有事」に的確に対応できていない問題だ。上記のように、宿泊療養確保が感染者増加に追いつかなかった、というが、それは認識違いではないか。別の報道によれば、全国の宿泊療養施設約28,000室の使用率は、1月末時点でたった23%程度、緊急事態宣言下にあった11都府県でもこぞって50%以下にとどまっている、という。既存の宿泊療養施設は有効活用されていないのだ。
その主な原因は、ワンフロアの陽性者全員が退所して初めてそのフロアを一斉消毒するケースが多く、稼働率が全く上がらず、宿泊療養施設が有効に使用できていない状態が生じていること、もう一つは、入院と宿泊療養のオペレーションを全て行っている保健所の業務がパンクしていることにあると思う。そのため、宿泊療養施設に入所できないまま、自宅療養が続き、容体が急変、亡くなる方が続出してきた、と言えそうだ。
2月3日に至り、厚労省コロナ対策本部から事務連絡が発出された。そこには「下記の事例等も参考にしていただき、宿泊療養施設の積極的な活用に取り組んで頂くよう、お願い致します」といささか突き放した言い回しで、好事例紹介としてフロアごとの一斉消毒に代え、退所者が出るごとにその部屋の消毒を行っている自治体や退所の翌日に直ぐに消毒をしている自治体が紹介されているだけだ。
何という「平時」の発想の対応だろうか。厚労省は、なぜ端的に「退所翌日に消毒を行い、施設使用率向上を図り、ひとりでも多くの陽性者に療養提供を可能とすること」と明確な指示を自治体に出さないのか。何人かの医師に訊いてみたが、新型コロナウィルスはどんなに長く生きてもせいぜい2〜3日という。また、元々無症状や軽症の「陽性者」が入る部屋であり、そこまで神経質になるよりも、どんどん療養施設に陽性者を入れ、自宅での容態急変による死亡リスクを回避することの方がずっと大事だ、との指摘ばかりだった。そもそも、自宅療養後の自宅の消毒についての厚労省の注意事項はあるものの、遵守されているかはおぼつかないはずだ。
さらに驚くのは、日本財団が昨年4月に、お台場の船の科学館近くに「野戦病院型病床」100床、「ペット同伴可能な仮設住居型病床」140室を設置表明され、現在東京都の宿泊療養施設として使用されているが、仮設住居型の方は、やはり消毒の制約から半分程度しか稼働可能ではない上に、現在は10人程度の入所にとどまっている。こうした医療資源の非効率運用を許すのは、「平時」の発想以外何物でもない。
消毒の問題に加えて、折角の「野戦病院型病床」は、厚労省の「宿泊療養マニュアル」における「居室は個室とする」という、まさに「有事」ではなく「平時」の発想の基準に反するとの理由で宿泊療養施設として使えず、そのままになっている。厚労省基準は、恐らく大部屋では他の感染症の感染リスクを排除できない、との「平時」の発想であるが、その「感染リスク」と、「容体急変リスク」を比較すれば、答えは一目瞭然だ。
私は、容態急変リスクを低減するため「自宅療養」は原則としてなくすべきと考えている。
英国医学誌のランセット誌のリチャード・ホートン編集長の著書『なぜ新型コロナは止められなかったのか』(青土社)によれば、中国はSARSの教訓から、今次パンデミックに際し、家庭内感染を阻止しながら検査・隔離を徹底して感染抑え込みを図るため、1000床規模の野戦病院型施設を16ほど作り、軽症者中心に徹底収容して、感染拡大と容体の急変事態への医療対応をして救命したという。科学的根拠に基づく「有事」の対処、と言えよう。
わが国で、「平時」の発想から「有事」の発想に転換できずに深刻な事態を招いている最も深刻な問題は、医療提供体制だ。私は、1月30日に「『薄く、広く』から『選択と集中』へ」として、あるべき「コロナ感染症の有事医療体制」をポンチ絵で提案した(注2)。非常事態宣言延長に際し、政府も「基本的対処方針」において、症状に応じた医療機関の役割分担の明確化や病床確保の推進、後方支援医療機関の確保等を提案しているが、そこでも「平時」の発想から抜け切れず、折角の方針が十分機能しないこととなる問題がある。それは、「有事」には不可欠な、そうした役割分担等の指示をする「司令塔」不在のままに、加えて各病院に人員確保を任せたまま役割分担せよ、との提案であり、それでは事態は大きく動かない。こうした対応策全体を知事、厚労大臣が総合調整し、場合によって指示も行える司令塔であることを明確化し、権限付与もすることが重要だが、今回の法改正ではそれが極めて不十分である。「平時」の武器で「有事」を克服しようとしても、それは無理だ。
さらに言えば、厚労省を含めた識者の中には、大学病院は、一般先端医療を引き続き受け持ち、コロナ医療は必ずしも担わなくて良い、との考えがあるが、私はそれも「平時」の発想だと思う。なぜならば、いまだにコロナは「未知の病」であり、「有事」には、国内はもとより、世界の英知を結集して治療法、予防法、ワクチン等を開発すべきで、ゲノム解析能力や医療設備的にも、先端医療を担う大学病院こそが「有事」の今、実力を発揮すべきと思う。米国ボストンのマサチューセッツ総合病院など、世界は平時に先端医療を担っている病院がコロナ重症患者を受け入れている。そして、多くの研究成果を世界の科学誌・医学誌で発表し、コロナ対策を推し進めている。
事程左様に、「平時」モードが随所に色濃く残り、「有事」体制が構築できていない制度、政策が多く残っているのが、わが国の特徴だが、これを覚悟を持って脱しないと、何時までも緊急事態と平常状態の繰り返しで、国民経済的に持たなくなることを強く危惧する。
(注1)「大規模感染症流行時の国家ガバナンス改革提言」、「大規模感染症流行時の国家ガバナンス見直しWG資料」
(注2)「『薄く、広く』から、『選択と集中』へ」
最大の焦点は、「有事には国が司令塔となり、責任を一手に負う」、すなわち「平時」通り、都道府県任せにはしない、ということを明確にし、全てを「有事」モードに切り替え、地方の声はよく聞きながら、最後は国が決めることだ。そうした大事なモードの大転換なしによって、本来助かる命が失われて来たのではないか、と与党議員の一人として責任を重く感じる。
昨年12月以降、全国で自宅療養中に亡くなった方々は少なくとも27人に上るという。そして、昨日の一部報道によると、その原因は第3波による感染者急増により宿泊施設確保が追いつかず、自宅療養者が急増、保健所の対応が追い付かず、死亡者が続出した、となっている。
この中には、いくつかの重要な認識違いがあり、その論理の裏にも、実は「平時」の発想のままで「有事」モードの体制構築ができていない結果、深刻な事態を招いているのでは、とみられる点が多々ある。
一番大きな認識違いからくる自宅待機中の死亡事例の根源的原因の一つは、新型コロナ感染症という、今だ未知な部分が多い、手強い感染症でありながら、相変わらず、陽性患者となった途端に保健所を中心とした「公衆衛生」の世界に患者を留め置き、それまで慣れ親しんできたかかりつけ医等の「地域医療」から隔絶させることだ。
保健所の職員の皆さんは、健康観察のため、電話で献身的に患者を気遣いながら、容体などを聞いてくれるものの、業務はパンク状態。病状が悪化しながら入院先を確保できず、患者は医師と話ができないうちに自宅で亡くなっていくケースが多いという。地域で自宅療養者の治療に当たっている数少ない医師の一人が昨日のテレビ画面を通じ「家族だけが保健所に入院先を探してもらえるよう折衝できるのであり、われわれ医師はそれができない」と、「有事」でありながら、「平時」通り「公衆衛生」優位が貫かれてしまう、もどかしい思いを吐露される姿が印象的だった。
昨年6月に私が自民党行革推進本部長として取りまとめた提言(注1)では、感染症危機対応体制に関し、「『公衆衛生」と『地域・臨床医療』の有機的一体化」を感染症有事における国家のガバナンス確立に向けての抜本改革の3本柱の重要なひとつとして提言した。コロナ危機を有効に乗り切ったと世界からみられている台湾、ベトナム、中国、韓国、などは、SARS、新型インフルエンザ、MARSなど感染症危機の教訓から、実際に「公衆衛生」と「地域臨床医療」との有機的一体化を既に実現し、今回もそれが機能しているという。陽性者の健康観察や入院先の調整を保健所、公衆衛生が独占する必然性はない。
二番目の問題は、宿泊療養について、「平時」の発想のままで「有事」に的確に対応できていない問題だ。上記のように、宿泊療養確保が感染者増加に追いつかなかった、というが、それは認識違いではないか。別の報道によれば、全国の宿泊療養施設約28,000室の使用率は、1月末時点でたった23%程度、緊急事態宣言下にあった11都府県でもこぞって50%以下にとどまっている、という。既存の宿泊療養施設は有効活用されていないのだ。
その主な原因は、ワンフロアの陽性者全員が退所して初めてそのフロアを一斉消毒するケースが多く、稼働率が全く上がらず、宿泊療養施設が有効に使用できていない状態が生じていること、もう一つは、入院と宿泊療養のオペレーションを全て行っている保健所の業務がパンクしていることにあると思う。そのため、宿泊療養施設に入所できないまま、自宅療養が続き、容体が急変、亡くなる方が続出してきた、と言えそうだ。
2月3日に至り、厚労省コロナ対策本部から事務連絡が発出された。そこには「下記の事例等も参考にしていただき、宿泊療養施設の積極的な活用に取り組んで頂くよう、お願い致します」といささか突き放した言い回しで、好事例紹介としてフロアごとの一斉消毒に代え、退所者が出るごとにその部屋の消毒を行っている自治体や退所の翌日に直ぐに消毒をしている自治体が紹介されているだけだ。
何という「平時」の発想の対応だろうか。厚労省は、なぜ端的に「退所翌日に消毒を行い、施設使用率向上を図り、ひとりでも多くの陽性者に療養提供を可能とすること」と明確な指示を自治体に出さないのか。何人かの医師に訊いてみたが、新型コロナウィルスはどんなに長く生きてもせいぜい2〜3日という。また、元々無症状や軽症の「陽性者」が入る部屋であり、そこまで神経質になるよりも、どんどん療養施設に陽性者を入れ、自宅での容態急変による死亡リスクを回避することの方がずっと大事だ、との指摘ばかりだった。そもそも、自宅療養後の自宅の消毒についての厚労省の注意事項はあるものの、遵守されているかはおぼつかないはずだ。
さらに驚くのは、日本財団が昨年4月に、お台場の船の科学館近くに「野戦病院型病床」100床、「ペット同伴可能な仮設住居型病床」140室を設置表明され、現在東京都の宿泊療養施設として使用されているが、仮設住居型の方は、やはり消毒の制約から半分程度しか稼働可能ではない上に、現在は10人程度の入所にとどまっている。こうした医療資源の非効率運用を許すのは、「平時」の発想以外何物でもない。
消毒の問題に加えて、折角の「野戦病院型病床」は、厚労省の「宿泊療養マニュアル」における「居室は個室とする」という、まさに「有事」ではなく「平時」の発想の基準に反するとの理由で宿泊療養施設として使えず、そのままになっている。厚労省基準は、恐らく大部屋では他の感染症の感染リスクを排除できない、との「平時」の発想であるが、その「感染リスク」と、「容体急変リスク」を比較すれば、答えは一目瞭然だ。
私は、容態急変リスクを低減するため「自宅療養」は原則としてなくすべきと考えている。
英国医学誌のランセット誌のリチャード・ホートン編集長の著書『なぜ新型コロナは止められなかったのか』(青土社)によれば、中国はSARSの教訓から、今次パンデミックに際し、家庭内感染を阻止しながら検査・隔離を徹底して感染抑え込みを図るため、1000床規模の野戦病院型施設を16ほど作り、軽症者中心に徹底収容して、感染拡大と容体の急変事態への医療対応をして救命したという。科学的根拠に基づく「有事」の対処、と言えよう。
わが国で、「平時」の発想から「有事」の発想に転換できずに深刻な事態を招いている最も深刻な問題は、医療提供体制だ。私は、1月30日に「『薄く、広く』から『選択と集中』へ」として、あるべき「コロナ感染症の有事医療体制」をポンチ絵で提案した(注2)。非常事態宣言延長に際し、政府も「基本的対処方針」において、症状に応じた医療機関の役割分担の明確化や病床確保の推進、後方支援医療機関の確保等を提案しているが、そこでも「平時」の発想から抜け切れず、折角の方針が十分機能しないこととなる問題がある。それは、「有事」には不可欠な、そうした役割分担等の指示をする「司令塔」不在のままに、加えて各病院に人員確保を任せたまま役割分担せよ、との提案であり、それでは事態は大きく動かない。こうした対応策全体を知事、厚労大臣が総合調整し、場合によって指示も行える司令塔であることを明確化し、権限付与もすることが重要だが、今回の法改正ではそれが極めて不十分である。「平時」の武器で「有事」を克服しようとしても、それは無理だ。
さらに言えば、厚労省を含めた識者の中には、大学病院は、一般先端医療を引き続き受け持ち、コロナ医療は必ずしも担わなくて良い、との考えがあるが、私はそれも「平時」の発想だと思う。なぜならば、いまだにコロナは「未知の病」であり、「有事」には、国内はもとより、世界の英知を結集して治療法、予防法、ワクチン等を開発すべきで、ゲノム解析能力や医療設備的にも、先端医療を担う大学病院こそが「有事」の今、実力を発揮すべきと思う。米国ボストンのマサチューセッツ総合病院など、世界は平時に先端医療を担っている病院がコロナ重症患者を受け入れている。そして、多くの研究成果を世界の科学誌・医学誌で発表し、コロナ対策を推し進めている。
事程左様に、「平時」モードが随所に色濃く残り、「有事」体制が構築できていない制度、政策が多く残っているのが、わが国の特徴だが、これを覚悟を持って脱しないと、何時までも緊急事態と平常状態の繰り返しで、国民経済的に持たなくなることを強く危惧する。
(注1)「大規模感染症流行時の国家ガバナンス改革提言」、「大規模感染症流行時の国家ガバナンス見直しWG資料」
(注2)「『薄く、広く』から、『選択と集中』へ」
- 2022/05/25 NO.875号
- 誰もが均しく最先端ゲノム医療を受けられる国へ
- 2022/05/07 NO.874号
- CEPI初の国際親善大使に任命
- 2022/04/24 NO.873号
- ゲノム解析による個別化医療を強力に推進
- 2022/04/04 NO.872号
- 自律機能なくして発展なし
- 2022/03/18 NO.871号
- 再び新たなスタート