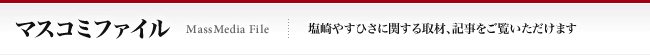論争 東洋経済-2001年3月号
金融動乱第ニ幕は資産市場の再構築がカギ
論争 東洋経済 2001年3月号
日本経済は、金融動乱の第二幕を迎えようとしている。日本の金融の中心テーマは、危機管理から、日本経済の生産性向上に金融業がいかに係わるかに移っている。そのカギを握るのが「資産市場の再構築」である。
グローバル化が着実に進展するなか、世界はダイナミックに変貌を続けている。その一方、先進国で日本の政治だけが司令塔不在のもとで、新しい国家ビジョンを示せず、多くの問題を先送りし続け、すでに10年が経過した。「これでは日本が潰れる」との切羽詰まった思いから湧きあがった「加藤政局」も、単なるトップ交代が目的ではなかったはずだ。経済政策や社会保障政策、教育政策に至るまで、根の深い問題への処方箋を示し、勇気をもって改革を開始せよ、という政策転換を求める「政策政局」にすべきであった。しかし、厳しい攻防の結果、この政変は明確な代替政策ビジョンの欠如から、結局、従来型の「権力闘争」として終わった。現政権は、高度はともかく、再び巡航しはじめたかにもみえている。だが、日本の抱える諸問題を解決する答えがない状況には何の変わりもない。日本の奥深くにじっと潜む病巣は放置されている。20世紀から持ち越された宿題を忘れたかのような政治に対して、市場は再び警告を発しはじめている。
21世紀日本の基本的視座
21世紀の日本は、グローバル資本主義の大きな流れから逃れられない。そのグローバル化によって日本がさらされる風や波に打ち勝ち、自立する道筋を示すことが、われわれに課せられた真の政治の役割である。
いま、グローバル化の荒波に向けて、政治が踏まえておくべき基本的な視座は次の3点ではないか。
第一に、中国やロシアといった地域不安定要因に対する戦略の構築である。第二次世界大戦後、50年以上の長きにわたって、日本は日米安保条約に頼って自由な世界貿易を安価に謳歌してきた。日本は自由な市場経済システムの受益者として、地域の不安定要因からシステムを守る役割を果たすために、自ら経済や安全保障のあり方を再設計すべき時期に差しかかっている。今後、中国やロシアといった潜在的な影響力の大きい国々や民族を、いかにわれわれと同質の市場経済システムに内包化させていくかが今後大きな課題である。そのために戦略的な視点から、われわれがもちうる政策手段を総合的に再構築していくべきである。
第二に、日本がリーディング・モデルを示すという気概である。明治維新以降、特にアジアの奇跡といわれた戦後の経済復興は、アジアのみならず多くの諸外国に対して希望の星となるモデルを示した。いま、企業統治や社会保障など多くの構造改革を抱えるのは、何も日本だけではない。例えば少子高齢化は先進国共通の問題であり、世界に先駆けて急速に高齢化が進む日本の政策は、重要なモデルを示すことになる。問題は、バブル崩壊以降、日本人は自らが国際的コミュニティーのなかで影響力のある存在であることを認識しない傾向が強くなったことである。この日本人自身の過小評価は、おそらく近年の日本やアメリカなどの政府がとってきた態度に影響されている。カネは出すが人は出さない小切手外交や、利権的な色彩が強くなったODAがそうした例だ。いまや優秀な若者は日本を飛び出し、リタイア組までが海外で何か役に立つことができないかと思いをめぐらせ、ボランティアをはじめとする国際的活動が盛んに行われている。つまり、現実の日本人に対応できていない国内のシステムが問題なのだ。
国際貢献でも、景気対策でも、本質的な問題解決を避けてとりあえずカネだけ出す、といったことを簡単にワシントンや東京の政治家や官僚が口にするような風潮がはびこるにつれて、自他ともに日本を過小評価する悪弊が目立ってきた。しかし、古い自民党的勢力が好む財政支出が極めて非効率なことは、多くの日本人が知ってしまった。今後は、国内の改革に関して、日本もアメリカも政府は世界のリーディング・モデルとなるべく建設的な政策立案を心がけるべきだ。
第三に、日本経済は、縮小均衡ではなく、生産性向上による拡大均衡を目指すべきことである。現在、日本の企業収益は生産性向上ではなく、資本や雇用の縮小によってもたらされている。1990年代を通じ経済の基盤が常に脆弱であった理由は、ここにある。日本の経済の問題は、財政による刺激の是非や民活云々という各論ではなく、日本の経済の資本と労働の収益率が国際水準より低い点をどうするかという、根幹の問題を避けては解決できない。典型的には民間や政府の不良資産問題のように、非効率な分野への資源が集中し、資源配分が歪められていることが、社会の生産性の向上を阻む要因となっている。それゆえこうした問題は、思い切って早目に抜本的な処理をすべきだ。
グローバル化は、資本や労働の値段を国際的に均等化させる圧力を生み出す。だからこそ、わが国の資本や労働の生産性を上昇させるための仕掛けこそが必要である。
競争政策の確立
もっとも、生産性向上と一言でいっても、単純ではない。経済のあらゆる部門で、生産性向上に向けた改革が必要となるからである。具体的には、企業、金融、そして政府の財政支出の分野である。
まず、企業では第一に、競争政策の強化を行うことが、生産性向上の最大のツールとなる。これは外国企業だけを潤すものではなく、日本の企業や消費者が究極受益者である。通信産業がその好例だ。実際に、アメリカ政府が日本の高いインターネット接続料金の問題を提起したとき、多くの日本の消費者はアメリカに賛成した。同様の図式は大規模流通店舗などの問題でも同様である。さらに、規制当局に関しては解決すべき多くの問題が残されている。
例えば、公正取引委員会の独立性や陣容の強化は競争政策上引き続き不可欠である。また、通信市場における開かれた競争を担保するためには、新設された総務省の傘下にある通信・放送行政を、新たに通信委員会として独立して創設することの是非も検討すべきである。
第二に、企業統治システムの改革は、競争政策に大きな影響を与える。現行商法は、株式分割、自由なストック・オプション、金庫株式など、多くの柔軟な企業金融取引を禁止しており、株主の権利や経営陣の義務などに関する大幅な見直しが必要である。法務省は商法を包括的に見直す作業に取り掛かっているが、私はそのスピーディーな見直しを求める。同時に透明な手続きを監視すべきだ。新設の経済産業省も、抜本的な商法の見直しを提言しているが、主要産業における自由な競争政策の強化という視点がより前面に出るべきだ。
「金融動乱」隠蔽から危機管理へ
経済の最大の問題は、引き続き金融にある。銀行に対する公的資本注入期限が3月末に迫っているなか、銀行の資本の再強化や借り手企業の改革などの問題に対して、いまだ不十分な手しか打たれていないことを、市場は見通している。 銀行への資本注入を決めた98年の早期健全化法は、われわれの主張に反して銀行の資産内容の厳格な査定を避ける法律の建前をとった。このボタンの掛け違えが間違いの始まりだ。プライドの高い銀行に政府が資本注入するために、「健全銀行に対して資本注入を行う」という一種のフィクションをとらざるをえなかった。その結果、各行への資本注入額が不十分となったうえ、優先株や劣後債という時間稼ぎにしかならない疑似資本の投入となった。しかし、これでは経営体力に欠ける銀行は返済を諦め、政府保有株を普通株に転換して固有銀行化するしか選択肢はない。また、公的資金を返済する銀行も、旧財閥グループに株式を引き取ってもらうくらいしか出口がない。
バブル崩壊から金融空洞化の危機が始まったのは、証券会社の損失補填が明るみになった91年、これが金融動乱の幕明け、いわば「長い序章」の始まりだった。初の公的資金導入を決めた95年の住専国会を経て、97年末の佐々波委員会に至るまで続いた「長い序章」のテーマは、「不良資産という問題の本質の隠蔽」にあった。ただし、この時期に金融空洞化への対応として金融ビッグバンというアジェンダを打ち立てることができた点は重要だ。国内勢が倒れた場合でも、国内のマネーとヒトの受け皿として外資系を東京市場に引き付けておくことは絶対条件だ。いま、資本市場におけるシェア、金融マンの転職の実体をみれば、その目的は達成している。皮肉に聞こえるかもしれないが、「ウィンブルドン化」はいまのところ日本経済のセーフティ・ネットとなっている。 金融動乱の「第一幕」で、98年春にわれわれ自民党の若手主導で進めた金融再生トータルプランとともに始まった。われわれが第一の項目として掲げたのは、資産内容の適正評価(デュー・デリジェンス)だ。資産評価の適正化を迫れば、銀行を追い込むことができる。追い込む先はゼロ金利の追い風のもとでの国有化である。金融再生法が必要となったのはこのためだ。また、不十分な内容だったが資本注入も実施し、その圧力の下で四大グループへの再編のメドもつけた。そして、日本経済の動脈である銀行を追い込めば、不良債権だけでなく、政府の保護の下にある弱い産業の改革を迫ることにつながる。だから、にわか仕込みだが民事再生法も成立させ、流通、ゼネコンをはじめ実際の企業破綻処理への適用が始まった。かねて主張してきた債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)も多くの企業破綻処理で応用されつつある。
こうした「第一幕」には、大銀行の破綻処理など日本が戦後一度も経験したことのないことが多発したため、打ち出された一連の政策に共通するテーマは「危機管理手法の確立」であった。それらの措置は危機管理であるゆえに、預金者保護、借り手保護、中小企業保護、既存産業保護、社会的弱者保護などさまざまな名目で、民間から政府へ巨額のリスクの付け替えが行われた。それが今日の645兆円の政府債務に積み上がった。
「第二幕」危機管理を超えて
いま、市場は再び株価の下落とともに金融動乱「第二幕」の始まりを告げている。それは、どのようなドラマになるのか。国民が「兆」という金額に慣れるほど膨れ上がった債務の山を前にして、これまで同様の危機管理手法を続けるべきだという風圧は強い。確かに、問題の端緒である不良債権額一つとっても、増え続けるばかりで危機的な状況である。四大金融グループといっても後ろ向きのリストラすら不十分であり、経営基盤は極めて脆弱だ。しかし、これらの風景自体は、「第一幕」ですでにみたことがあるものばかりだ。銀行破綻、生保破綻、企業処理等々。われわれはすでにそうした問題の対処手法を知っているし、日本人の気持ちのうえでも、もはや大企業の破綻自体は大事件ではなくなってしまった。そうである以上、危機管理の名のもとに目をつぶり将来子供たちが背負う国の借金を増やし続けるわけにはいかない。
実は、「第二幕」の中心テーマは、危機管理を超えて、金融システムが日本経済の生産性向上にいかに寄与できるか、そして金融業自体が高い生産性を実現できるかにあると考えている。この問題を解くカギは、いかに安定的かつ効率的な資産市場をつくれるか、にかかっている。90年代の長い経済停滞の原因が、資産バブルの後遺症、端的には自己査定で80兆円以上の不良債権がその本質である以上、国内の余剰貯蓄のリスク・マネー化への転換を行いながら、株式、社債、不動産など国内の民間資産市場の活性化を図ることでしか、本源的な意味でバランスシートの呪縛を解き、資産の収益率を高める方法はないからだ。この資産市場の再構築こそ、上述した経済の生産性を高めるための競争政策の触媒となる。
具体的にみてみよう。重要な点は、金融機関が集めたカネをいかに「国債ではない」民間のリスク・マネーに転化していくか、にある。つまり、民間企業の株式、社債や不動産など資産市場にマネーが環流していく装置を再構築すること、言い換えれば、家計の過剰貯蓄である預貯金をリスク・マネーに振り替えるために、国内勢の受け皿を構築することが課題である。それができなければ、現に市場で起こりつつある国債への投資集中が一層進むであろう。実際、資本注入後、銀行による国債保有額は30兆円から60兆円に倍増した。このままでは、資産の海外逃避が加速し、外資系が国内市場を独占し、国内勢は総崩れしていくことも避けられない。4月以降も、総理や関係閣僚等が出席する金融危機対応会議の下で、銀行に資本注入や国有化を行う道は残されている。しかし、資本注入をした資金で金融機関が国債を買うだけの効果しかない政策は、もはや採るべきではない。そのカネが企業整理や金融再編という中身のある改革につながらないかぎり、資本注入を行っても意味はない。それでは、どのような方向で金融再構築が行われていくべきなのか。金融の専門家の指摘は、次のような点に絞られている。
第一に、脱預金化、脱貸し出し化である。金融機関のバランスシートから負債を切り離す手段として有効なのは、銀行顧客がATMでも使えるような投資信託口座の提供である。同時に、資産サイドでも、貸し出しのオフバランス化によってリスクにふさわしいリターンを得るための資産の圧縮、資産効率の向上を図る。
第二に、流行りの言葉でいえば選択と集中、イメージしやすい言葉でいえば金融工場化である。例えば、リテイルは中小金融機関が強みを生かせる分野だが、大銀行が同じような自転車作戦のリテイル戦略を採っていては覚束ない。金融技術の進展を生かし、スケールメリットが生かせる金融工場化(融資審査工場、金融商品工場、アセットマネジメントの外部調達など)を進めるべく組織を作り替える。つまり、世界屈指の競争力をもつ日本の自動車メーカーのビジネス・モデルに学ぶわけだ。
第三に、こうした方向のなかで、大金融グループと地域金融機関とが合従連衡を行う。脱預金化、脱貸し出し化、金融工場化によって、部門ごとのアンバンドリング(切り離し)が進み、タテヨコの合従連衡が行いやすくなるからだ。
こうした成功例の一つは、米銀の「タンデム化」である。アメリカの銀行規制は、歴史的に州際業務を禁止してきたが、80年代後半のS&L危機のときに州をまたいだ大銀行による弱小金融機関の救済買収が解禁された。例えば、「シティバンクFSB(Federal Saving Bank)」と呼ばれている法人がそれだ。法人格自体は買収前のS&L(貯蓄銀行)のままで、シティバンク本体である「シティバンクNA」とはあくまで別会社である。ところが、シティバンクに買収、系列化され、外見、看板、業務仕様、取扱商品やサービス、ATMに至るまで同一であり、例えば預金の預け替え等も同一銀行内のようにシームレスでサービスを提供する。弱い金融機関の預金の受け皿をソフトな形で用意するタンデム化は、大規模な預金流出に最も効果的なだけでなく、より洗練された脱預金商品の提供、そしてスケールメリットを生かした金融工場化を進めることができる手法である。
資産市場復活に向けての制度的条件
ただし、こうした合従連衡の金融再編を通じた株式、社債、不動産等の資産市場復活のためには、大きな条件が残されている。それはこれまでのように不透明な「ニギリ」や「もたれあい」で正確な収益力が測定できない世界とは訣別し、「不断の競争圧力」が日本の金融業や資産市場にかかるようにすべき点である。具体的には、以下のような課題が挙げられる。
第一は、独立した日本版SECの創設である。昨年春以降のITバブル崩壊によって、日本の証券市場は本質的な弱さを露呈した。わが国は伝統的に、株価操作やインサイダー取引などに対する法の執行体制が甘いといわれてきたが、特にベンチャー企業では浮動株比率の低さや最低純資産額規制などが相まって、不透明な取引を生みやすい素地がある。日本版SECの創設による法の執行体制の強化により、わが国の証券市場の信頼回復に地道に取り組むべきだ。
第二に、会計基準設定主体の民営化、独立性の強化である。本年夏から日本の会計基準設定主体は、従来の政府の会計審議会から、アメリカのFASBのような民間の会計基準設定主体に民営化されるが、その透明かつ厳正な運営の確保が重要である。日本の会計基準は、これまで「飛ばし」を生む甘い連結基準や、銀行が保有する有価証券の低価法容認など相次ぐ粉飾決算的な措置によって世界の投資家からの信頼を失った。しかも、いまでさえ銀行の長期保有有価証券の時価計上延期を求める声すら一部に聞かれている。会計基準設定主体の民営化だけでなく、日本版SECを創設することは、会計基準の設定プロセスの厳正化に資することになる。
第三は、投資信託の独立性の確保である。日本の投資信託はその多くが証券会社の系列企業であり、証券会社との利益相反措置が他の先進国に比べて徹底されていない。なかには証券会社の自己売買のごみ箱とまで揶揄する者すらいるありさまだ。実際、鳴り物入りで導入したファンドの基準価格が素人の株式投資にも劣るといわれるなど、同業界の抜本的な信頼回復は急務だ。資産運用規模の中長期的な拡大を最優先目標とする手数料体系に再構築し、同時に利益相反措置を強化徹底するなどの改革に直ちに着手すべきである。
第四に、資産課税体系の抜本的な見直しである。高齢社会に向けて、預貯金や国債などの安全資産や相続対策上捕捉しにくい資産への集中が進むなかで、国内のリスク・マネーのチャネルをいかに確保するか、という視点から税制の哲学を根本的に見直すべきだ。具体的には、納税者番号制導入を前提とする株式の申告課税への移行や資産所得の捕捉などと同時に、リスク・マネーを適切に取り扱うためのキャピタル・ゲインの繰り延べ、キャピタル・ロスの繰り越しといった措置を、株式等の有価証券だけでなく、広く不動産、SPC出資証券、ベンチャー企業投資等に認めるべきである。不動産を例にとってみよう。不良債権の担保不動産を処理するためには、誰かが不動産を買わねばならない。担保不動産の売り手は含み損を抱える一方で、担保不動産の買い手はすでに保有している不動産の含み益をもっている。それゆえ、いわば同種の投資の「交換」である不動産の買い替え時のキャピタル・ゲインを何度でも繰り延べられれば、買い手は意欲を刺激され、取引が活性化する。キャピタル・ゲインの繰り延べ、キャピタル・ロスの繰り越しといった措置は、資産市場再生へのドライビング・フォースになるとともに、マクロ経済的にも適切な資源配分や高い収益率が達成できる。昨年末の自民党税調では、UPREITというスキームを提案し、継続的な検討課題となっているが、これも含み益をもつ優良な不動産の課税を繰り延べて、市場に放出させるための仕組みである。
政治のチャレンジ
以上のような競争政策、基本法則、資本市場、税制等にかかる課題の解決を図らねば、今後10年間において、日本経済の空洞化は一層深刻化すると同時に、世界との軋轢が激化するだろう。政府の財政支出の効率化や財政改革を行う際には、資本の国外流出や輸出を加速させる可能性がある以上、同時に国内市場の開放など国際的に互恵的な枠組みで取り組む必要がある。そこで、自由貿易協定(FTA)といわれる措置が有効になろう。今後日本はこれまで以上に、世界の自由貿易や安全保障の受益者となるはずであり、その対価として国内の市場を世界に提供することで国際的な信頼をかちえねばならない。もちろん、政治家として、財政改革と同時にこうした課題をこなしていくことは、国内的に痛みを伴うことは理解している。だからこそ、有権者に対する説明責任がある政治家自身が国民を引っ張っていかなくてはならない。
最後に、こうした双方向の改革による経済のグローバル化は、必ずしも文化や社会の同質化を意味しない点を強調しておきたい。経済のグローバル化に対しては感情的な攘夷論が高まりがちだが、実は、逆説的に日本社会の特質を生かすことを通じてこそ、グローバル化のなかではより高い収益率を上げられるのである。これは比較優位の貿易理論が教えるところである。例えば、日本では少なくとも普通の働き手の基礎的な知的水準が国際的にみて高いとか、チームワークの協調性による品質管理や改善運動が優れているといった特質は、国際的には比較優位をもつ重要な点だ。むしろ、日本の長所を生かして、今後いかなる新分野にわれわれが資源を投入していくか、という決断こそが問われているのである。
- 緊張感が生む強い企業
- 日本経済新聞2024年12月11日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年5月9日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年4月20日掲載記事
- 世界のサカモト、僕の坂本 前衆院議員塩崎恭久さん 坂本龍一さん追悼
- 愛媛新聞ONLINE-2023年4月14日掲載記事
- 開始延期を支持した「大臣談話」公表の真意―塩崎恭久元厚労相に聞く
- 日本最大級の医療専門サイト m3.comインタビュー記事