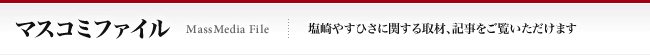日本経済新聞 2001年12月1日
減損会計2003年度にも導入 「金融庁方針 含み損処理 企業に迫る」
金融庁方針 含み損処理 企業に迫る
金融庁は土地や工場など固定資産の価値が下がった場合に損失処理を義務づける「減損会計」を早ければ2003年度(2004年3月期)から導入する方針を固めた。国際的な会計基準に合わせ、企業経営の実態をより正確に把握し投資家の信頼を高める狙い。減損会計は企業に巨額の含み損処理を迫ることになり、企業の再編淘汰(とうた)を一段と促すきっかけとなりそうだ。
金融庁の担当官が自民党金融調査会企業会計小委員会(委員長・塩崎恭久衆院議員)で、遅くとも2004年度から導入の方針を示した。委員会のメンバーを中心に自民党では2003年度からの導入を強く求める声が多く、導入が1年早まる可能性もある。
金融庁が減損会計の導入時期を示したのは初めて。金融庁の企業会計審議会が来年6月に「減損会計基準」の公開草案を公表、一般の意見を聞いたうえで来年内に基準を確定する。その後、実務指針などを作成し、遅くとも2004年4月以降始まる決算期(2005年3月期)から企業が選択適用できるようにする。金融庁では全上場企業に適用を義務づけるのは2005年度(2006年3月期)とする考えだ。
減損会計は企業が持つ資産の時価が帳簿価格を下回った場合、その差額を損失として計上するよう義務づける会計基準。株式など金融商品と販売用不動産には部分的に導入されているが、土地や建物といった固定資産全般を対象にした基準はまだない。基準がないのは先進国では日本だけで、日本企業の決算書の信頼回復に向け早期の導入が課題になっている。
減損会計が導入されるとバブル期に取得した土地に多額の含み損を抱えるゼネコンなどが損失計上を迫られるほか、稼働率が低下して計画通りの収益を上げていない工場などの価値の見直しも必要になる。上場企業が保有する帳簿上の土地は50兆円とみられ、5兆―10兆円規模の損失計上を迫られるとの見方もある。
減損会計2003年度にも 含み損処理待ったなし
【解説】
金融庁が減損会計導入のスケジュールを示したことで、いよいよ企業が持つ土地や建物、工場といった資産の含み損処理が待ったなしになる。企業が全体でどれくらいの損失処理を迫られるかは不明だが、上場企業(新興市場上場企業と銀行証券保険を除く2078社)の「土地」勘定だけでも50兆円を超えることを考えると、影響は小さくない。
バブル期に不動産投資などを拡大したゼネコン(総合建設会社)や不動産業界には、減損会計導入が「退場勧告」になりかねない企業が多い。すでに義務づけられている販売用不動産の減損処理での損失表面化を避けるために、自社利用不動産に勘定科目を変更して損失処理を先送りしている会社もある。その一方で、日立製作所やコマツなど優良企業は損失を前倒し処理しており、減損会計導入を機に格差が表面化する可能性がある。
減損会計の影響は、土地投機などバブルに踊った企業ばかりではない。1980年代後半から90年代前半にかけて新工場の建設など、生産能力を大幅に増やす例が相次いだ。その後の景気後退で、こうした工場が過剰設備となっているケースは少なくなく、高いままになっている「帳簿価格」を時価に引き下げることが求められる。
減損会計が義務づけられている米国では、半導体メーカーなどが市況低迷で収益回収が見込めなくなった製造設備の損失を一気に計上する例が多い。
日本でも今後、電機メーカーなどの間で、同様の損失処理が義務づけられることになる。
【減損会計】
▽…企業が持つ資産の時価が帳簿価格を大幅に下回ったときに、その差額の損失処理を義務づける会計基準。日本では土地や建物、工場設備といった固定資産については明確な基準がない。米国基準や国際会計基準にはすでに減損会計が導入されており、国際化を目指す日本の会計基準において最大の課題となっている。
▽…半導体メーカーなどでは多額の資金を投じて建設した最新鋭の工場設備の稼働率が市況の低迷などで悪化。時価で評価し直せば、巨額の損失が発生し過剰設備の実態が明らかになる可能性がある。バブル期に取得した土地に多額の含み損を抱える建設会社や生命保険に与える影響も懸念されている。
金融庁は土地や工場など固定資産の価値が下がった場合に損失処理を義務づける「減損会計」を早ければ2003年度(2004年3月期)から導入する方針を固めた。国際的な会計基準に合わせ、企業経営の実態をより正確に把握し投資家の信頼を高める狙い。減損会計は企業に巨額の含み損処理を迫ることになり、企業の再編淘汰(とうた)を一段と促すきっかけとなりそうだ。
金融庁の担当官が自民党金融調査会企業会計小委員会(委員長・塩崎恭久衆院議員)で、遅くとも2004年度から導入の方針を示した。委員会のメンバーを中心に自民党では2003年度からの導入を強く求める声が多く、導入が1年早まる可能性もある。
金融庁が減損会計の導入時期を示したのは初めて。金融庁の企業会計審議会が来年6月に「減損会計基準」の公開草案を公表、一般の意見を聞いたうえで来年内に基準を確定する。その後、実務指針などを作成し、遅くとも2004年4月以降始まる決算期(2005年3月期)から企業が選択適用できるようにする。金融庁では全上場企業に適用を義務づけるのは2005年度(2006年3月期)とする考えだ。
減損会計は企業が持つ資産の時価が帳簿価格を下回った場合、その差額を損失として計上するよう義務づける会計基準。株式など金融商品と販売用不動産には部分的に導入されているが、土地や建物といった固定資産全般を対象にした基準はまだない。基準がないのは先進国では日本だけで、日本企業の決算書の信頼回復に向け早期の導入が課題になっている。
減損会計が導入されるとバブル期に取得した土地に多額の含み損を抱えるゼネコンなどが損失計上を迫られるほか、稼働率が低下して計画通りの収益を上げていない工場などの価値の見直しも必要になる。上場企業が保有する帳簿上の土地は50兆円とみられ、5兆―10兆円規模の損失計上を迫られるとの見方もある。
減損会計2003年度にも 含み損処理待ったなし
【解説】
金融庁が減損会計導入のスケジュールを示したことで、いよいよ企業が持つ土地や建物、工場といった資産の含み損処理が待ったなしになる。企業が全体でどれくらいの損失処理を迫られるかは不明だが、上場企業(新興市場上場企業と銀行証券保険を除く2078社)の「土地」勘定だけでも50兆円を超えることを考えると、影響は小さくない。
バブル期に不動産投資などを拡大したゼネコン(総合建設会社)や不動産業界には、減損会計導入が「退場勧告」になりかねない企業が多い。すでに義務づけられている販売用不動産の減損処理での損失表面化を避けるために、自社利用不動産に勘定科目を変更して損失処理を先送りしている会社もある。その一方で、日立製作所やコマツなど優良企業は損失を前倒し処理しており、減損会計導入を機に格差が表面化する可能性がある。
減損会計の影響は、土地投機などバブルに踊った企業ばかりではない。1980年代後半から90年代前半にかけて新工場の建設など、生産能力を大幅に増やす例が相次いだ。その後の景気後退で、こうした工場が過剰設備となっているケースは少なくなく、高いままになっている「帳簿価格」を時価に引き下げることが求められる。
減損会計が義務づけられている米国では、半導体メーカーなどが市況低迷で収益回収が見込めなくなった製造設備の損失を一気に計上する例が多い。
日本でも今後、電機メーカーなどの間で、同様の損失処理が義務づけられることになる。
【減損会計】
▽…企業が持つ資産の時価が帳簿価格を大幅に下回ったときに、その差額の損失処理を義務づける会計基準。日本では土地や建物、工場設備といった固定資産については明確な基準がない。米国基準や国際会計基準にはすでに減損会計が導入されており、国際化を目指す日本の会計基準において最大の課題となっている。
▽…半導体メーカーなどでは多額の資金を投じて建設した最新鋭の工場設備の稼働率が市況の低迷などで悪化。時価で評価し直せば、巨額の損失が発生し過剰設備の実態が明らかになる可能性がある。バブル期に取得した土地に多額の含み損を抱える建設会社や生命保険に与える影響も懸念されている。
- 塩崎氏ら3人がアフガンへ出発 〜NGO活動視察〜
- 愛媛新聞-2001年12月18日
- 本四架橋 夢のあと -公団31年の決算-「まずは責任の検証から」
- 朝日新聞-2001年12月12日
- 迅速な政策転換実現へ首相直轄の「政策室」設置を
- 週刊東洋経済「視点」-2001/12/08 号
- 政策実現にはスピード必要 党幹部は閣内に入れ
- 毎日新聞-2001年12月3日
- 減損会計2003年度にも導入 「金融庁方針 含み損処理 企業に迫る」
- 日本経済新聞 2001年12月1日