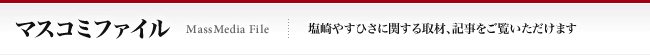日本経済新聞 2001年11月11日
減損会計2003年度にも導入 「金融庁方針 含み損処理 企業に迫る」
NGOを生かす
政治と連携、外交に厚み
市民社会が企業文化変える
政治と非政府組織(NGO)の距離が急速に縮まっている。自民党は市民運動を出発点とすることが多いNGOとは疎遠だったが、窓口組織を作るなど姿勢が変化し始めた。何が変わったのか。同党でパイプ役を務める衆院議員の塩崎恭久氏に聞いた。
―― 米英の攻撃が続くアフガニスタンでは大量の難民流出がが予想され日本のNGOの活躍が期待されます。政治の後押しは?
日本から駆けつけた団体はまだ、アフガン国境付近などに拠点を設けることができませんが、情勢が落ち着けば本格的な活動が始まります。その時にわれわれも現地に行き、一緒に活動する必要があると考え、タイミングをみています。彼らだけではパキスタン政府や国連との連絡がうまくいかないかもしれない。議員外交との有機的な連携をはかれればと思います。
―― 自衛隊派遣で活動がしにくくなるとの声もあります。
NGOは自衛隊とは目的が全く違う活動をするわけです。日本が国際社会の中でどういう地位を占めるべきかを考えることと、NGOの活動とは別物です。NGOは独自の援助を貫徹する以外にないと思います。
―― 昨年、自民党内に「国際的NGOに関する小委員会」ができ塩崎さんが委員長に就きました。何が変わったのですか。
党の外交部会長としてコソボ難民支援で日本の国際的NGOが活動した話を聞き、また国連経済制裁が続くイラクでは日本の大使館員もいない中、クルド難民支援で活躍していることもわかりました。そこで政治の側も変わる必要があると感じ、昨年、税制改正で非営利組織(NPO)の支援税制を導入する際、支援に動くことになりました。それも政府ではなく彼らの側に立つ支援ができないかと考えたのです。
「政府」対「政府」だけが外交ではない。「人間」対「人間」のつながりの重要性を考えると、正式な外交に民間パワーによる国際的なつながりが加われば、「トラック・ツー(第二のルート)」のある、厚みある外交が可能になります。
例えば、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の問題。政府の外交と人道援助は直接関係ないのが世界の常識ですが、日本は感情的に割り切れない傾向があります。外務省は国交の有無など形式にこだわりがちです。日本人拉致(らち)問題の解決は重要ですが、国益を考えれば、もう少し柔軟な対応ができるのではないか。米国の場合、北朝鮮とミサイル問題の話し合いをしながら、米国の民間団体が現地でリンゴの木を植え、長期支援を続けています。現在、北朝鮮では結核が流行しており、医療支援ができないか、NGOのみなさんと話し合いをしています。
―― NGOは自主独立が基本で、政治の介入には敏感です。第二のルートという考えは、外交を補完するわけではないとの反発を招きませんか。
政府が第二のルートになれとお願いするわけではありません。あくまで自然に、二つの流れができるということです。NGOやNPOは官が決めた公益のために活動しているわけではない。民が公益と考えることを実現するために動きます。それが結果として外交政策にもなるといういうことです。外交とは別に人道支援はきちんと存在します。目の前に傷ついた人がいれば、助けるべきか、とは悩まないでしょう。助けることが公益にかない、その役割を民が担うのです。
―― 政治が動き、支援税制ができましたが、要件が厳しく利用しにくいとの声があります。前回、ジャパン・プラットフォームの大西代表も指摘しました。
個人や法人からのNPOへの寄付金を所得などから控除できる支援税制は10月にスタートしたばかりです。使い勝手の良さなどについて意見を聞き、改正が必要かどうか考えたい。一人が多額の寄付をした場合、一部しか控除の対象にならない場合がある点がよく批判されます。このルールはあくまでも支援の広がりを見るためのもので、実際に寄付を受けることとは別の問題です。
それよりも(国連開発計画など)国際機関から多額の委託金を受けた場合どう扱うか、海外への送金時に事前に額や使い道の届け出が必要といった点が問題だと考えています。活動資金を集めるための(書籍販売など)収益事業で得た利益を、軽減税率で非営利活動に使える「みなし寄付金制度」も認められていません。これも今後の課題です。
―― 政府開発援助(ODA)予算のうちNGOを対象とするものは十分ではありません。
今年度予算で言えば、NGO対象の補助金などは約40億円。来年度予算の要求ベースでも約55億円です。ODA全体にしめる割合も、外務省は2.4%と言っているが、1%未満という説もある。いずれにしても、米国が15.7%、カナダ8.9%、英国11.7%に比べれば、微々たるものでしかない。さらなる努力が必要です。
来年度予算では、NGOの意見も聞いた上で、7つの支援メニューを盛り込んだ「NGO支援レインボー・プログラム」を創設する予定です。ここにはかねて要望があった、事務所の管理費用などにもお金を使える仕組みを作りました。また、外務省の窓口も一本化して、要求に素早くこたえられるようにします。
―― 8月末に東ティモールに行き、現地で日本や欧米のNGOの活動を見たそうですね。日本は人材面で遅れていませんか。
コソボの時は日本は存在感を十分発揮するまでに苦労したが、東ティモールでは頑張っている。1年半で約5千戸のトタン屋根の修理を日本のNGOだけでやったそうです。山の尾根から見ると、あちこちで屋根がきらきら光り壮観でした。一流企業を辞めた女性や大学院修了者がいて頼もしかった。
それでも、人材不足は否めません。育成するには、大学がボランティア活動を単位として認めるなど自発的に活動できる環境を整える必要があります。高校で奉仕活動を義務づけるとの議論がありましたが、強制はボランティア(志願者)の意味に反します。
人材交流も促したい。ジャパン・プラットフォームの事務局長が日本航空から来ているように、企業との交流は増えつつあります。しかし、外務省本省へは皆無です。同省の民間援助支援室長をNGOから登用するようなことが必要でしょう。
―― 人材や製品提供、寄付など企業も支援に動き出していますが、さらに貢献できませんか。
米国の企業は地域などへの貢献を前面に出し企業文化をアピールします。しかし日本ではまだ、そうした貢献が企業目的の1つという発想にはなっていない。結局、企業統治(コーポレートガバナンス)の問題です。米国では株主が抱く企業の未来イメージを予測して経営が決まる。利益だけでなく環境に優しいとか、人道支援もするとか、株主は企業が何を重視しているかを考える。日本は資本市場が発達しておらず、企業は株主のもの、という発想がないのです。日本全体が、NGOなどのいわゆる「市民社会(シビルソサエティー)」を尊重する社会に変わることが企業文化を変えるでしょう。
―― 日本は本当に、そうした社会に変われるでしょうか。
変われなければ、企業も含めて日本は世界の中で取り残されるだけです。阪神大震災であれだけ学生ボランティアが生まれました。素地は十分にあります。後は自立した市民が思いっきり活動できる土俵を政治が作ることです。私も政治家を辞めた後に、NGOで活動してみたいと思っています。
政治と連携、外交に厚み
市民社会が企業文化変える
政治と非政府組織(NGO)の距離が急速に縮まっている。自民党は市民運動を出発点とすることが多いNGOとは疎遠だったが、窓口組織を作るなど姿勢が変化し始めた。何が変わったのか。同党でパイプ役を務める衆院議員の塩崎恭久氏に聞いた。
―― 米英の攻撃が続くアフガニスタンでは大量の難民流出がが予想され日本のNGOの活躍が期待されます。政治の後押しは?
日本から駆けつけた団体はまだ、アフガン国境付近などに拠点を設けることができませんが、情勢が落ち着けば本格的な活動が始まります。その時にわれわれも現地に行き、一緒に活動する必要があると考え、タイミングをみています。彼らだけではパキスタン政府や国連との連絡がうまくいかないかもしれない。議員外交との有機的な連携をはかれればと思います。
―― 自衛隊派遣で活動がしにくくなるとの声もあります。
NGOは自衛隊とは目的が全く違う活動をするわけです。日本が国際社会の中でどういう地位を占めるべきかを考えることと、NGOの活動とは別物です。NGOは独自の援助を貫徹する以外にないと思います。
―― 昨年、自民党内に「国際的NGOに関する小委員会」ができ塩崎さんが委員長に就きました。何が変わったのですか。
党の外交部会長としてコソボ難民支援で日本の国際的NGOが活動した話を聞き、また国連経済制裁が続くイラクでは日本の大使館員もいない中、クルド難民支援で活躍していることもわかりました。そこで政治の側も変わる必要があると感じ、昨年、税制改正で非営利組織(NPO)の支援税制を導入する際、支援に動くことになりました。それも政府ではなく彼らの側に立つ支援ができないかと考えたのです。
「政府」対「政府」だけが外交ではない。「人間」対「人間」のつながりの重要性を考えると、正式な外交に民間パワーによる国際的なつながりが加われば、「トラック・ツー(第二のルート)」のある、厚みある外交が可能になります。
例えば、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の問題。政府の外交と人道援助は直接関係ないのが世界の常識ですが、日本は感情的に割り切れない傾向があります。外務省は国交の有無など形式にこだわりがちです。日本人拉致(らち)問題の解決は重要ですが、国益を考えれば、もう少し柔軟な対応ができるのではないか。米国の場合、北朝鮮とミサイル問題の話し合いをしながら、米国の民間団体が現地でリンゴの木を植え、長期支援を続けています。現在、北朝鮮では結核が流行しており、医療支援ができないか、NGOのみなさんと話し合いをしています。
―― NGOは自主独立が基本で、政治の介入には敏感です。第二のルートという考えは、外交を補完するわけではないとの反発を招きませんか。
政府が第二のルートになれとお願いするわけではありません。あくまで自然に、二つの流れができるということです。NGOやNPOは官が決めた公益のために活動しているわけではない。民が公益と考えることを実現するために動きます。それが結果として外交政策にもなるといういうことです。外交とは別に人道支援はきちんと存在します。目の前に傷ついた人がいれば、助けるべきか、とは悩まないでしょう。助けることが公益にかない、その役割を民が担うのです。
―― 政治が動き、支援税制ができましたが、要件が厳しく利用しにくいとの声があります。前回、ジャパン・プラットフォームの大西代表も指摘しました。
個人や法人からのNPOへの寄付金を所得などから控除できる支援税制は10月にスタートしたばかりです。使い勝手の良さなどについて意見を聞き、改正が必要かどうか考えたい。一人が多額の寄付をした場合、一部しか控除の対象にならない場合がある点がよく批判されます。このルールはあくまでも支援の広がりを見るためのもので、実際に寄付を受けることとは別の問題です。
それよりも(国連開発計画など)国際機関から多額の委託金を受けた場合どう扱うか、海外への送金時に事前に額や使い道の届け出が必要といった点が問題だと考えています。活動資金を集めるための(書籍販売など)収益事業で得た利益を、軽減税率で非営利活動に使える「みなし寄付金制度」も認められていません。これも今後の課題です。
―― 政府開発援助(ODA)予算のうちNGOを対象とするものは十分ではありません。
今年度予算で言えば、NGO対象の補助金などは約40億円。来年度予算の要求ベースでも約55億円です。ODA全体にしめる割合も、外務省は2.4%と言っているが、1%未満という説もある。いずれにしても、米国が15.7%、カナダ8.9%、英国11.7%に比べれば、微々たるものでしかない。さらなる努力が必要です。
来年度予算では、NGOの意見も聞いた上で、7つの支援メニューを盛り込んだ「NGO支援レインボー・プログラム」を創設する予定です。ここにはかねて要望があった、事務所の管理費用などにもお金を使える仕組みを作りました。また、外務省の窓口も一本化して、要求に素早くこたえられるようにします。
―― 8月末に東ティモールに行き、現地で日本や欧米のNGOの活動を見たそうですね。日本は人材面で遅れていませんか。
コソボの時は日本は存在感を十分発揮するまでに苦労したが、東ティモールでは頑張っている。1年半で約5千戸のトタン屋根の修理を日本のNGOだけでやったそうです。山の尾根から見ると、あちこちで屋根がきらきら光り壮観でした。一流企業を辞めた女性や大学院修了者がいて頼もしかった。
それでも、人材不足は否めません。育成するには、大学がボランティア活動を単位として認めるなど自発的に活動できる環境を整える必要があります。高校で奉仕活動を義務づけるとの議論がありましたが、強制はボランティア(志願者)の意味に反します。
人材交流も促したい。ジャパン・プラットフォームの事務局長が日本航空から来ているように、企業との交流は増えつつあります。しかし、外務省本省へは皆無です。同省の民間援助支援室長をNGOから登用するようなことが必要でしょう。
―― 人材や製品提供、寄付など企業も支援に動き出していますが、さらに貢献できませんか。
米国の企業は地域などへの貢献を前面に出し企業文化をアピールします。しかし日本ではまだ、そうした貢献が企業目的の1つという発想にはなっていない。結局、企業統治(コーポレートガバナンス)の問題です。米国では株主が抱く企業の未来イメージを予測して経営が決まる。利益だけでなく環境に優しいとか、人道支援もするとか、株主は企業が何を重視しているかを考える。日本は資本市場が発達しておらず、企業は株主のもの、という発想がないのです。日本全体が、NGOなどのいわゆる「市民社会(シビルソサエティー)」を尊重する社会に変わることが企業文化を変えるでしょう。
―― 日本は本当に、そうした社会に変われるでしょうか。
変われなければ、企業も含めて日本は世界の中で取り残されるだけです。阪神大震災であれだけ学生ボランティアが生まれました。素地は十分にあります。後は自立した市民が思いっきり活動できる土俵を政治が作ることです。私も政治家を辞めた後に、NGOで活動してみたいと思っています。
- 緊張感が生む強い企業
- 日本経済新聞2024年12月11日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年5月9日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年4月20日掲載記事
- 世界のサカモト、僕の坂本 前衆院議員塩崎恭久さん 坂本龍一さん追悼
- 愛媛新聞ONLINE-2023年4月14日掲載記事
- 開始延期を支持した「大臣談話」公表の真意―塩崎恭久元厚労相に聞く
- 日本最大級の医療専門サイト m3.comインタビュー記事