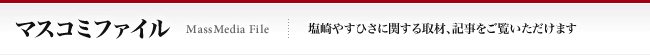朝日新聞-2017年12月1日掲載記事
(耕論)里親は根付くか: 高い目標、現状変える力に 塩崎恭久さん(前厚生労働相、衆議院議員)

家庭とは遠い環境です。自分の子どもだったら、こうするでしょうか。特定の大人と愛着を育むことが大切な時期には、事情がある子どもたちであっても施設ではなく、家庭と同じような環境で育てるべきだと感じていました。
「法律に書かないと実態は変わらない」という強い思いがあります。日本は、国際条約の児童の権利条約に批准しながら、親の権利は民法に明記しても、子どもの権利はどこにもなく国際的に見ても異例でした。厚生労働相だった昨年、児童福祉法を改正し、第1条に子どもの権利を明記し、第3条で家庭的養育優先の原則を明確にしました。
里親の委託率目標を掲げた今年8月の厚労省のビジョンは、この法改正をどう具体的に進めていくか、「原則」を数値化したものです。逆に甘すぎるくらいかもしれません。ここまでしないと、現状は変えられないのです。
里親への委託率は現在17%程度で、未就学の子の75%とした目標は高すぎ、現実離れしているという意見もあります。しかし、試算すると人口120万人の都市で年9人の里親を増やせば達成できます。突拍子もない目標ではないのです。
特別養子縁組を倍増させる目標も非現実的だと言われますが、実際は原則6歳未満という年齢制限などの制度の問題で断念しているケースも多くあります。法改正も含めた制度改正を、現在は法務省が検討しています。
成り手は、児童相談所と民間機関がもっと連携して協力しながら進めれば、増やせます。施設も高度な専門性を生かし、受け入れ以外の役割もお願いします。難しい環境に置かれた子どもたちの問題に一番くわしいのは、経験がある施設の人たち。地域で特別養子縁組の養親や里親を支援する役割を果たしてほしい。児童相談所だけでは手が回らないので、生活の身近にいる市区町村も一緒に組んで、責任を担ってもらいます。
「理想が高くてできるわけがない」と言っているその1日の間に、子どもに影響が出て、虐待で亡くなる子も出てくるかもしれません。その責任はどうやってとるのでしょうか。法律があっても現状は何も変わらないことは、いくらでもあります。与党の国会議員として、国や自治体などの動きが、改正法や新ビジョンにきちんと合っていくことを確認していきます。
(聞き手・西村圭史)
*
しおざきやすひさ 1950年生まれ。2014年9月〜今年8月に厚生労働相。児童の養護と未来を考える議員連盟会長も務める。
〇朝日新聞インターネット記事へのリンクはこちらになります。ぜひご覧下さい。
※本件記事は、朝日新聞社に無断で転載することが禁じられています。(承諾番号 17-6494)
- FRIDAYインタビュー記事
- FRIDAY-2023年3月22日掲載記事
- 日刊ゲンダイ インタビュー記事
- 日刊ゲンダイ-2021年3月18日掲載記事
- (耕論)里親は根付くか: 高い目標、現状変える力に 塩崎恭久さん(前厚生労働相、衆議院議員)
- 朝日新聞-2017年12月1日掲載記事
- 特集「どんな親でも必要なのは愛」塩崎恭久氏が語る里親と特別養子縁組のこれから 〜"子どもの権利"の法制化に努力した元厚労相〜
- 【インタビュー記事】ハフポスト日本版
- 【対談】 働き方・休み方改革 ―生産性の向上と誰もが活躍できる社会の実現に向けて
- 月刊経団連 7月号