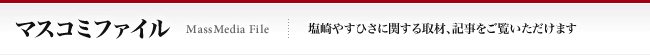NIKKEI NET 特別コラム「ザ・フロントランナー今週の視点」第7回-2002/02/11 号
原点を忘れた政府系金融機関改革
昨年の特殊法人の見直しにおいて、政府系金融機関の見直しについては、住宅金融公庫は5年後廃止、他の機関については経済財政諮問会議で検討される事となった。当然我々自民党行革推進本部においても今後並行して改革案を作成することとなろう。
政府系金融の見直しに当たっては、その原点に立ち帰らねばならない。例えば日本政策投資銀行法第21条(業務の条件)には「その業務の運営に当たっては一般の金融機関の行なう金融等を補完し、または奨励することとし、これらと競争してはならない」と言い切っている。今日の銀行の足腰の弱さをもたらした原因のひとつが政府系金融であるとの指摘を念頭に、民間経済の発展に寄与する事はもちろん、21世紀の民間金融の発展に資するよう、その役割を再定義しなくてはならない。
しかし、相変わらず所管官庁や政府系金融機関にはその原点を忘れたような動きが見られるだけでなく、政治家や利用者のなかにもそれを是とする傾向がある点が気がかりだ。一つの例が「事業再生融資(DIPファイナンス)」である。
これは再建型倒産法制である民事再生法、会社更生法を利用している事業者の事業継続のためにニューマネーを供給するもので、米国でも80年代以降、一般化している。民事再生法適用申請が急増している日本でも、一旦破綻した企業を再び蘇らせるためには必須の融資制度だが、これまでのところ、民間の銀行もノンバンクも及び腰だ。そこで経済産業省は政府系金融機関である日本政策投資銀行や中小公庫にその「呼び水」役を担わせようとしてきている。
発想は分からないでもない。しかし、実際に起きている事は、「親方日の丸」であるが故にコスト観念の薄い政府系金融機関がDIPファイナンス市場の価格(金利)形成を歪め、民間金融機関が想定するリスクプレミアムよりはるかに低い金利で融資するかたちで、結果として民間金融機関と競合し、時に民間金融機関を押しのけているとさえ聞く。
そもそも米国で一般的でありながら日本の民間金融機関がDIPファイナンスに及び腰なのには別の理由がある。その根本原因を是正しなければ、政府系金融は永久に「呼び水」役を続けなければならなくなってしまう。その原因とは、米国と異なりDIPファイナンスが法的に十分守られていないが故に、最終的に回収不能となる場合があり得るということだ。米国では再建手続き中の共益債権のなかで、最優先弁済を認めるスーパープライオリティなどDIPファイナンスに対していくつかの法的保護措置が担保されており、企業再建が容易になっている。わが国でも、租税債権、労働債権との関係や既存担保権者との関係など法制上の難問を立法府の知恵と決断で解決する事によって根本的な隘路を取り除き、民間がリスクに見合った利益を享受しながら、同融資を活発化し、未曾有の経済苦境を克服するのが筋だろう。根本原因の解決せずして政府系金融に役割を担わせるのは、本末転倒だし、民業圧迫である。
また、銀行がこの融資を再生中の企業に行なうと「不良債権」とされてしまう惧れが残っていることも、銀行が消極的な理由のようだ。これとて金融庁の行政判断と立法府の決断で解決できようが、そのためにも上記の法的措置整備が不可欠のはずだ。
いずれにしても、経済の主役はあくまでも民間企業と民間金融機関。政治の役割はその土俵作りだ。民間の一層の努力も期待されるが、少なくとも公的セクターは民間の邪魔をせず、民間の背中を押す役に徹するように制度設計をしなくてはならない。
政府系金融の見直しに当たっては、その原点に立ち帰らねばならない。例えば日本政策投資銀行法第21条(業務の条件)には「その業務の運営に当たっては一般の金融機関の行なう金融等を補完し、または奨励することとし、これらと競争してはならない」と言い切っている。今日の銀行の足腰の弱さをもたらした原因のひとつが政府系金融であるとの指摘を念頭に、民間経済の発展に寄与する事はもちろん、21世紀の民間金融の発展に資するよう、その役割を再定義しなくてはならない。
しかし、相変わらず所管官庁や政府系金融機関にはその原点を忘れたような動きが見られるだけでなく、政治家や利用者のなかにもそれを是とする傾向がある点が気がかりだ。一つの例が「事業再生融資(DIPファイナンス)」である。
これは再建型倒産法制である民事再生法、会社更生法を利用している事業者の事業継続のためにニューマネーを供給するもので、米国でも80年代以降、一般化している。民事再生法適用申請が急増している日本でも、一旦破綻した企業を再び蘇らせるためには必須の融資制度だが、これまでのところ、民間の銀行もノンバンクも及び腰だ。そこで経済産業省は政府系金融機関である日本政策投資銀行や中小公庫にその「呼び水」役を担わせようとしてきている。
発想は分からないでもない。しかし、実際に起きている事は、「親方日の丸」であるが故にコスト観念の薄い政府系金融機関がDIPファイナンス市場の価格(金利)形成を歪め、民間金融機関が想定するリスクプレミアムよりはるかに低い金利で融資するかたちで、結果として民間金融機関と競合し、時に民間金融機関を押しのけているとさえ聞く。
そもそも米国で一般的でありながら日本の民間金融機関がDIPファイナンスに及び腰なのには別の理由がある。その根本原因を是正しなければ、政府系金融は永久に「呼び水」役を続けなければならなくなってしまう。その原因とは、米国と異なりDIPファイナンスが法的に十分守られていないが故に、最終的に回収不能となる場合があり得るということだ。米国では再建手続き中の共益債権のなかで、最優先弁済を認めるスーパープライオリティなどDIPファイナンスに対していくつかの法的保護措置が担保されており、企業再建が容易になっている。わが国でも、租税債権、労働債権との関係や既存担保権者との関係など法制上の難問を立法府の知恵と決断で解決する事によって根本的な隘路を取り除き、民間がリスクに見合った利益を享受しながら、同融資を活発化し、未曾有の経済苦境を克服するのが筋だろう。根本原因の解決せずして政府系金融に役割を担わせるのは、本末転倒だし、民業圧迫である。
また、銀行がこの融資を再生中の企業に行なうと「不良債権」とされてしまう惧れが残っていることも、銀行が消極的な理由のようだ。これとて金融庁の行政判断と立法府の決断で解決できようが、そのためにも上記の法的措置整備が不可欠のはずだ。
いずれにしても、経済の主役はあくまでも民間企業と民間金融機関。政治の役割はその土俵作りだ。民間の一層の努力も期待されるが、少なくとも公的セクターは民間の邪魔をせず、民間の背中を押す役に徹するように制度設計をしなくてはならない。
- 緊張感が生む強い企業
- 日本経済新聞2024年12月11日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年5月9日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年4月20日掲載記事
- 世界のサカモト、僕の坂本 前衆院議員塩崎恭久さん 坂本龍一さん追悼
- 愛媛新聞ONLINE-2023年4月14日掲載記事
- 開始延期を支持した「大臣談話」公表の真意―塩崎恭久元厚労相に聞く
- 日本最大級の医療専門サイト m3.comインタビュー記事