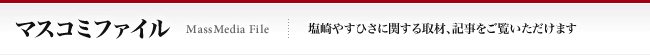週刊東洋経済「視点」-1999/05/15 号
日本の会計制度に信頼を取り戻そう

また今、クレディ・スイス・ファースト・ボストン問題(含み損の"とばし"疑惑)が注目されているが、これが象徴的に物語るのは海外から「日本の会計基準なら、母国ではできない会計操作によって商売ができる」と思われていたことだ。 数年前、外資系金融機関の若手デリバティブズ専門家から「"とばし"などの会社決算操作のお手伝いは日常業務」と聞き、ショックを受けた。日本の企業経営者は決算・財務をごまかすうえ、日本の会計基準の不備を突けばいろいろできる、とまで海外に思われていたのだ。
会計基準は単に「会計」の問題ではない。国際的に信頼されなければ、ジャパンプレミアムを通じた資金調達コストの上昇等によって、企業や企業への投資家にとどまらず、一般会計もデメリットを被る結果となることを忘れてはならない。
我が国では、このように重要な経済インフラである会計基準を大蔵省の権限のもと、企業会計審議会が設定してきた。税効果会計や時価会計の導入など、大蔵省の努力もあり基準自体はかなりグローバル・スタンダードに近づいてきたが、その設定主体については省庁再編等の議論でも正面から取り上げられないまま今回の財・金分離協議の中で、その権限が金融庁に移ることとなった。
しかし、会計基準には経済・社会の変化に応じた不断の見直し、整備が必要だ。国際的に見ても国際会計基準委員会(IASC)がグローバル基準設定等を行う常設の基準開発委員会(SDC)を作る計画をしていることを考えると、日本の会計基準を企業会計審議会という非常勤メンバーで構成され、若干の大蔵省担当者を除き常駐者もおらず、常設機関でもない組織にいつまでも任せるわけにはいくまい。また常駐者が事実上いない現状ではSDCに誰が参加するか決めようもない。
本来、会計基準は民間のルールである。いつまでも「お上が作ったものを授かる」発想はいただけない。米国SECから権限委譲されているFASB(財務会計基準審議会)は独立した純粋民間組織である。米国とともに国際会計基準(IAS)を主導する英国、カナダ等でも常勤メンバーのいる民間団体が実質的な設定主体だ。ドイツも昨年FASB的な民間組織を作った。しかも各国とも基準審議のメンバーは専門家が実質的な議論をできる人数(米、独は7人)にとどめ、会計士・企業財務担当者のウエートが高い。基準設定過程も極めて透明で、FASBやIASCの会議は完全公開だ。
日本におけるガバナンス改革を行う今、会計制度も既存の審議会を若干手直しする程度でお茶を濁しては、日本の国際的信頼回復はできない。少なくとも会計基準設定主体は独立性の高い、民間の専門家を中心とした常設機関にすべきだ。
- 日本の会計制度に信頼を取り戻そう
- 週刊東洋経済「視点」-1999/05/15 号
- 「日本版ビッグバン」から「サプライサイド改革」へ
- Foresight(フォーサイト)「政治家の仕事」-1999年5月15日号掲載
- 為替相場は誰のもの?
- 週刊東洋経済「視点」-1999/04/10 号
- 企業の不良資産処理急げ
債務の株式化で再生を - 日本経済新聞「日経オピニオン」 1999年3月29日
- 「債務の株式化」(デット・エクイティ・スワップ)を導入せよ
過剰債務解消の第一歩は、既存債務と株式の交換から - 週刊東洋経済「視点」1999年3月27日号掲載