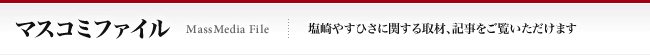旬刊 経理情報-2000年3月10日号
脱・会計鎖国には政治の出動が必要
旬刊 経理情報 2000年3月10日号
会計基準設定のインフラを早急に整備して国の信頼回復を
国際的に通用するわが国の会計基準は、誰が、どんなプロセスを踏んで作るのか― いわゆる会計基準設定主体をどうするかが緊急の課題になっている。
編集部からの要請は、自民党金融問題調査会の企業会計に関する小委員会報告「企業会計基準設定主体の拡充・強化に向けて」のまとめ役をつとめた私に、その考え方を披瀝せよ、とのものであるが、とくに、かつて企業会計の問題に政治が出動することなどはなかったが、この度特段の関わり持つことの意味も問いたい、とのようである。紙幅の制約があって意を尽くせないが、考えの一端を述べてみる。
昨年、わが国の3月決算会社が海外向けに作成した英文の監査報告書に「この財務諸表は、日本において一般に認められた会計基準に従うものであり、日本以外の国で一般的に通用している会計基準に従って作成された会計内容の開示とは異なる…」という警句(レジェンド)が付けられた。
相次ぐ金融機関・企業の破綻や、もっと前から疑惑ありと見られていた含み損の飛ばし問題などが顕在化して、監査法人が訴えられるケースすら出てきた。この警句は"ビッグ5"と言われる世界五大会計事務所の要請があって、日本の監査法人がそれに応じたものとされているが、そうした事情の如何にかかわらず、「日本の会計制度は国際レベルでは信頼に足りない」ということに違いはなく、企業はもちろん国自体の信頼失墜と受け止めなければならない。会計鎖国の日本に黒船:レジェンドが開国を迫っているのである。会計基準は世界で一本化する方向に動いている。このままでは、日本は世界の流れに取り残される。信頼失墜は日本企業の資金調達コストに影響する。ジャパン・プレミアムだ。これを突き詰めると、そのコストは国民全体が負担することを意味しており、国の問題である。こうした状態は放置できるものではなく、政治も含めて、会計制度に関わる者は、一刻も早く信頼を取り戻すために努力を怠ってはならない。会計基準設定問題は、まさにその中核をなす課題なのである。ここに来て、所管官庁である大蔵省、公認会計士協会、経団連などにおいても危機感をもった本格的な対応が始まっている。まことに結構なことである。
ただ、ご承知のように、国際会計基準委員会(IASC)は大きな組織改正を行い、主要各国の会計基準設定主体の代表者による議論によって、ダイナミックに変化する企業ないし経済活動に能動的に対応できる統一的会計基準を作るという新体制が間もなく発足することになっている。伝えられるところでは、IASCにおけるわが国の存在感は極めて希薄なものになり、発言にパワーを持てそうにないことになるやも知れない、と危惧されている。そうした事態は何としても回避しなくてはならない。
わが国の新しい会計基準設定主体のあり方についてのディテールは、「小委員会中間報告(案)」に委ねるが、関係者がこぞってこの問題に真剣な取り組みをされているとき、積極的にこれを支援していくことが、政治に課せられた責務でもある。
強力な資本市場を育て、一元的な責任体制をつくり、経済の変化にダイナミックに対応していくという国の政策は明確である。そして、そのベースを形成するものが、実は会計基準であることを認識すれば、その設定主体のあり様こそ早急に決め、「日本は変わった」と世界に向けて宣言をしなければならない、と思量するところである。
- 官民の人材「流動化」で霞が関を建て直せ(5月6日合併号)
- 週刊東洋経済「視点」-2000/04/29 号
- ネットが変える政策の作り方
- 週刊東洋経済「視点」-2000/04/01 号
- 脱・会計鎖国には政治の出動が必要
- 旬刊 経理情報-2000年3月10日号
- 投資銀行(インベストメントバンク)の内幕
- 週間東洋経済-2000年3月4日
- 企業会計制度の決定 だれが(自民企業会計小委 塩崎恭久・小委員長に聞く)
- 日経産業新聞-2000年2月29日