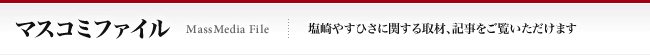日本経済新聞夕刊-2008年4月14日掲載記事
こころの玉手箱①「高校時代の制帽 〜自由を渇望、闘う生徒会長」
すべてに渇望していた。ベトナム戦争時、世界中で反戦運動が渦巻いていた。
都立新宿高校に通っていた私はヘーゲル、サルトル、バタイユなどの本を抱えて朝は新宿のジャズ喫茶「ピット・イン」で友だちと待ち合わせ。放課後は社会科学研究会で「日本はどうあるべきか」と国家を語り合った。学校の中庭に日の丸の国旗を立て、吉本隆明氏の著書「共同幻想論」に触れながら議論したこともあった。
二年生の夏、米サンフランシスコ郊外の高校に留学した。あらゆるものが新鮮だった。反戦集会に参加した。「私はこの戦争に反対だ」。目の前で演説したのは当時、カシアス・クレイと名乗ったボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリだった。
ロックの聖地、サンフランシスコ市内のフィルモア・ウェストにも足を運んだ。ライブで直接聞いたジミ・ヘンドリックス、クリーム、ピンク・フロイドなどのLPを山ほど仕入れて日本に持ち帰った。
一九六八年。ヒッピー全盛の米国から、長髪にジーンズで真っ黒に日焼けして戻ってきた私には、日本の高校は息苦しかった。制服制帽、授業もガチガチにみえた。思い切って生徒会長に立候補した。
「自由で人間味のある教育」を公約に掲げ、学校の象徴でもある制服制帽の着用義務付けの廃止を訴えた。留学から戻って一学年下がったので友人は二、三年生と二学年にわたる。生徒会長に当選した。任期は十月から翌年の三月まで。
その前後、パリでカルチェ・ラタン、中国では文化大革命、そして米国ではアポロが月面に着陸した。六七年末に公開されたダスティン・ホフマン主演の「卒業」とそのテーマ曲であるサイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」を聞くと、当時の記憶が鮮やかに蘇る。時代はものすごいスピードで変わっていった。
日本でも東大安田講堂事件が起き、騒然としていた。私は生徒会長の任期ギリギリの三月に制服制帽着用の自由化に何とかこぎつけ公約を実現した。生徒会長を辞めた後も闘い続けた。二年生を誘い、校長室を占拠。政治活動の自由を求め、十日間のストライキも打った。
自由でありたいという気持ちを抑えることはできなかった。
都立新宿高校に通っていた私はヘーゲル、サルトル、バタイユなどの本を抱えて朝は新宿のジャズ喫茶「ピット・イン」で友だちと待ち合わせ。放課後は社会科学研究会で「日本はどうあるべきか」と国家を語り合った。学校の中庭に日の丸の国旗を立て、吉本隆明氏の著書「共同幻想論」に触れながら議論したこともあった。
二年生の夏、米サンフランシスコ郊外の高校に留学した。あらゆるものが新鮮だった。反戦集会に参加した。「私はこの戦争に反対だ」。目の前で演説したのは当時、カシアス・クレイと名乗ったボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリだった。
ロックの聖地、サンフランシスコ市内のフィルモア・ウェストにも足を運んだ。ライブで直接聞いたジミ・ヘンドリックス、クリーム、ピンク・フロイドなどのLPを山ほど仕入れて日本に持ち帰った。
一九六八年。ヒッピー全盛の米国から、長髪にジーンズで真っ黒に日焼けして戻ってきた私には、日本の高校は息苦しかった。制服制帽、授業もガチガチにみえた。思い切って生徒会長に立候補した。
「自由で人間味のある教育」を公約に掲げ、学校の象徴でもある制服制帽の着用義務付けの廃止を訴えた。留学から戻って一学年下がったので友人は二、三年生と二学年にわたる。生徒会長に当選した。任期は十月から翌年の三月まで。
その前後、パリでカルチェ・ラタン、中国では文化大革命、そして米国ではアポロが月面に着陸した。六七年末に公開されたダスティン・ホフマン主演の「卒業」とそのテーマ曲であるサイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」を聞くと、当時の記憶が鮮やかに蘇る。時代はものすごいスピードで変わっていった。
日本でも東大安田講堂事件が起き、騒然としていた。私は生徒会長の任期ギリギリの三月に制服制帽着用の自由化に何とかこぎつけ公約を実現した。生徒会長を辞めた後も闘い続けた。二年生を誘い、校長室を占拠。政治活動の自由を求め、十日間のストライキも打った。
自由でありたいという気持ちを抑えることはできなかった。
- 緊張感が生む強い企業
- 日本経済新聞2024年12月11日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年5月9日掲載記事
- Governance Q 対談記事
- Governance Q-2023年4月20日掲載記事
- 世界のサカモト、僕の坂本 前衆院議員塩崎恭久さん 坂本龍一さん追悼
- 愛媛新聞ONLINE-2023年4月14日掲載記事
- 開始延期を支持した「大臣談話」公表の真意―塩崎恭久元厚労相に聞く
- 日本最大級の医療専門サイト m3.comインタビュー記事