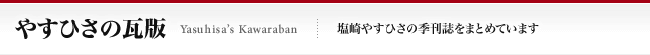1999/12/21
やすひさの瓦版(特別号)
企業会計基準設定主体の拡充・強化に向けて(案)
平成11年12月21日
自由民主党・金融問題調査会
企業会計に関する小委員会
近年、監査証明を受けた金融機関が結果的に多額の債務超過を抱えていたり、わが国会計基準を悪用した「損失隠し」の横行等から、わが国会計制度への信頼は大きく揺らいでいる。ここにきて国際会計基準に準拠した時価会計、連結会計導入等のインフラ整備が急速に進められてきているが、本年に入り日本基準に基づく英文の監査証明書には日本独特のものであり、国際水準とは異なるとの警句(レジェンド)の記述が強制されるなど、わが国の会計、監査制度に対する国際的な不信感は依然根強い。また、こうした事を背景に、国際会計基準設定の新たな動きへのわが国の積極関与も危ぶまれる状況である。
会計制度は、究極的にはコーポレートガバナンスに関わる事であるが、何と言ってもディスクロージャーをベースとした金融資本市場の基本的インフラであり、その整備無くしてはビッグバンの総仕上げはありえない。当小委員会は、会計制度の迅速かつ抜本的改革が不可欠との認識のもと、本年8月以来計11回に及ぶ会合を開催し、(1)会計基準設定主体の強化・拡充、(2)ルール執行・監督主体の強化・拡充、(3)公認会計士・監査法人の役割・責任の明確化・充実などをテーマに、所管官庁、公認会計士協会、経団連、資本市場関係者、学者などからのヒアリング等を精力的に行った。その結果、信頼回復に向け取り組むべき諸問題のうち、まずは中間報告として、会計制度の中心とも言うべき会計基準設定主体の改革につき、以下の提言を行うこととした。
なお、本件については、国際会計基準設定の新たな枠組みがスタートする2001年初までにその具体的骨格が示されている事が望ましい事に留意すべきである。
I.会計基準設定主体のあり方と改革の方向
会計基準設定主体の使命は、以下の3点に集約される。
諸外国を見ると、米国では、会計基準の設定権限は行政機関のSECに属するものの、実際の設定自体は民間団体のFASBに権限が委譲されている。また英国でも同様に、基準設定は民間団体のASBに権限委譲されている。
さらにわが国同様、従来、行政府が直接基準設定を行っていたドイツでも、連結会計については商法が指定する民間団体のDRSCに策定させ、報告を受けた司法省が公示を行い、それを遵守すれば、正規の簿記原則を遵守したものと「推定する」こととなった。この結果、先進国では、フランスだけが大蔵大臣の諮問機関(CNC)に基準設定の役割を担わせている。
以上のような諸点を踏まえて検討した結果、当委員会は、会計基準設定主体の問題は国家戦略的に取り組むべき課題との見方で一致すると共に、わが国における設定主体のあり方については、現行の企業会計審議会に代えて、以下のような新たな枠組みを構築すべきとの結論に達した。
今後の取り運びについては、本件が企業活動の根幹に関わる重要問題であることを深く認識し、公認会計士協会、経済界、大蔵省・法務省・通商産業省等関連行政庁などと、広範な開かれた議論を早急に深め、連立与党間での合意により、早期に成案を得るよう取り組む所存である。
II.今後早急に答えを出すべきその他の課題とその方向性
なお、これまでの会合で十分議論が尽くせなかったが、重要な問題として、今後、継続的に議論すべき課題とその向かうべき方向は以下の通り。
平成11年12月21日
自由民主党・金融問題調査会
企業会計に関する小委員会
近年、監査証明を受けた金融機関が結果的に多額の債務超過を抱えていたり、わが国会計基準を悪用した「損失隠し」の横行等から、わが国会計制度への信頼は大きく揺らいでいる。ここにきて国際会計基準に準拠した時価会計、連結会計導入等のインフラ整備が急速に進められてきているが、本年に入り日本基準に基づく英文の監査証明書には日本独特のものであり、国際水準とは異なるとの警句(レジェンド)の記述が強制されるなど、わが国の会計、監査制度に対する国際的な不信感は依然根強い。また、こうした事を背景に、国際会計基準設定の新たな動きへのわが国の積極関与も危ぶまれる状況である。
会計制度は、究極的にはコーポレートガバナンスに関わる事であるが、何と言ってもディスクロージャーをベースとした金融資本市場の基本的インフラであり、その整備無くしてはビッグバンの総仕上げはありえない。当小委員会は、会計制度の迅速かつ抜本的改革が不可欠との認識のもと、本年8月以来計11回に及ぶ会合を開催し、(1)会計基準設定主体の強化・拡充、(2)ルール執行・監督主体の強化・拡充、(3)公認会計士・監査法人の役割・責任の明確化・充実などをテーマに、所管官庁、公認会計士協会、経団連、資本市場関係者、学者などからのヒアリング等を精力的に行った。その結果、信頼回復に向け取り組むべき諸問題のうち、まずは中間報告として、会計制度の中心とも言うべき会計基準設定主体の改革につき、以下の提言を行うこととした。
なお、本件については、国際会計基準設定の新たな枠組みがスタートする2001年初までにその具体的骨格が示されている事が望ましい事に留意すべきである。
I.会計基準設定主体のあり方と改革の方向
会計基準設定主体の使命は、以下の3点に集約される。
- 常に国内外の経済実態を迅速かつ正確に反映した基準の設定
- 特定の利害関係者によって歪められない会計基準の設定
- 国際的整合性を持った基準の設定
- 常設の機関であること
- 常勤の設定委員、常勤の専門スタッフをもつこと
- 政治・特定省庁、特定業界、特定学派などから、政策面はもとより予算や人事面等を含め、独立性をもつこと
- 透明性が高いこと(設定委員の選出過程、会計基準の設定議事の公開等)
- 国際性をもつこと
- 会計、監査基準に多様な価値観を反映させることができること
- 能動的な基準設定を行うためのダイナミズムをもつこと
諸外国を見ると、米国では、会計基準の設定権限は行政機関のSECに属するものの、実際の設定自体は民間団体のFASBに権限が委譲されている。また英国でも同様に、基準設定は民間団体のASBに権限委譲されている。
さらにわが国同様、従来、行政府が直接基準設定を行っていたドイツでも、連結会計については商法が指定する民間団体のDRSCに策定させ、報告を受けた司法省が公示を行い、それを遵守すれば、正規の簿記原則を遵守したものと「推定する」こととなった。この結果、先進国では、フランスだけが大蔵大臣の諮問機関(CNC)に基準設定の役割を担わせている。
以上のような諸点を踏まえて検討した結果、当委員会は、会計基準設定主体の問題は国家戦略的に取り組むべき課題との見方で一致すると共に、わが国における設定主体のあり方については、現行の企業会計審議会に代えて、以下のような新たな枠組みを構築すべきとの結論に達した。
- まず、会計基準設定権限を付与すべき行政庁を国家の意思として明確にする。
- その上で、ドイツのDRSC方式を参考とし、当該権限を有することとされた行政庁が最終的な設定権限を留保しつつ、上記7つの条件を満たす民間法人を指定し、そこへ会計基準設定機能を委任する。
---なお、任期の長い複数の常勤委員を置くこと等により、現行企業会計審議会や会計基準担当部局の強化等で対処すべき、との意見もあった。 - ただし、問題の緊急性に鑑み、こうした新たな設定主体がスタートするまでの暫定的かつ一時的な措置として、早急に現行の企業会計審議会や会計基準担当部局等、会計基準設定関連組織の拡充を図ることで、新たな設定主体への移行を迅速かつ円滑に行うこととする。
今後の取り運びについては、本件が企業活動の根幹に関わる重要問題であることを深く認識し、公認会計士協会、経済界、大蔵省・法務省・通商産業省等関連行政庁などと、広範な開かれた議論を早急に深め、連立与党間での合意により、早期に成案を得るよう取り組む所存である。
II.今後早急に答えを出すべきその他の課題とその方向性
なお、これまでの会合で十分議論が尽くせなかったが、重要な問題として、今後、継続的に議論すべき課題とその向かうべき方向は以下の通り。
- 証券取引等監視委員会の役割・責任の明確化・強化とその組織的位置付けの見直し
---「損失補填問題」への反省から創設された同委員会をビッグバン後の資本市場監督主体(ルール執行主体)としてどう位置付けるかについては、その機能を上記の会計基準設定権限などと共に糾合し、「日本版SEC」のような、有効に機能する新たな三条委員会を創設すべきとの意見が示された。
---また、見直しに当っては、金融行政関連機構の簡素化、一元化等の観点にも十分留意すべき、との見方が示された。 - 公認会計士、監査法人の使命・役割・責任の明確化・強化
---昭和23年に制定された公認会計士法の全面改正を行い、公認会計士、監査法人の使命、役割、責任を明確化・強化すると共に、その独立性を高めるべき、との見方が多かった。 - 商法会計と証取法会計の関係整理
---eコマースの進展など変化の著しい実体経済を絶えず的確に反映する会計基準作りと、配当可能利益との関係で厳格さが求められる会計処理との関係整理が必要との見方で一致。 - 国内における国際会計基準の容認の是非
---今後さらに検討。 - 公会計基準の設定
---特殊法人、公益法人、特別会計をはじめとする公的セクターの会計処理基準の明確化の必要性についての指摘があり、その基準設定主体のあり方についてさらに検討。